
コロナブルーを乗り越える本 阿古智子
現代中国学者の阿古智子さんが紹介する本は、20世紀初頭、東アジアの人々とペストとの闘いを政治、医療などの面から分析しています。コロナとの闘いが終わるとき、世界はどのような姿をしているのでしょう?
※この記事は、集英社インターナショナル公式サイトで2020年5月5日に公開された記事の再掲載です。
『衛生と近代―ペスト流行にみる東アジアの統治・医療・社会』
永島剛・市川智生・飯島渉編/法政大学出版局
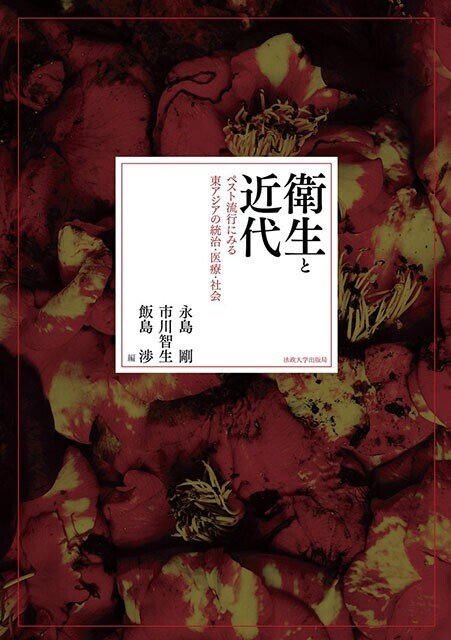
「鼠疫」、つまりペスト(腺ペスト)が北里柴三郎によって歴史上初めて医学的に確認されたのは、1894年、香港においてであった。不介入主義を貫く英国統治下の香港では、ヨーロッパ系住民と中国系住民の居住区は分離していたが、中国系住民が増加する中、中国人コミュニティでもイギリス流の衛生行政が行われるようになった。
その16年後の1910年、上海の共同租界でもペスト騒動が起こった。中国人は強制隔離や戸別検査など、専門化された近代医療の空間や手法に馴染めず、西洋人の男性医師や検査官を恐れる中国人女性たちは子どもを連れて逃げまどった。「顔色の黄色い人は衛生員に見つかると強制的に隔離される」「隔離病院では隔離された人の体を原料に薬を作っている」といったデマが広がる中、中国人たちが、検査に訪れた衛生員や医師を取り囲み、検査を妨害するという事件が相次いで発生した。
「ペスト検査を上流の中国人は理解しているが、下流の中国人は理解できずに恐れている」「愚民がデマに振り回されて騒動を起こしている」「中下等の人たちが恐れて騒ぎ、暴動を起こした」といった当時の上海の新聞記事からは、「上流―下流」「西洋人―中国人」といった対立軸を固定した見方が広がっていたことがわかる。このような中で、偏見や差別が助長され、感染症への恐怖から、極度に「自己」を防衛する欲求が高まり、「他者」に対しては憎悪さえ生んでいたのだった。
デマや差別の根源を探ると、医学や生活習慣の差異が生じさせた誤解、社会に元々根付いていた分断の構図が見えてくる。ペストの時代から100年以上経ち、ほとんどの地域で植民地統治が終わった現在も、そうした状況はあまり変わっていないのではないか。
私たちはコロナ禍に怯え、苦しむなかで、国内外で科学や医学に関して、統治や管理の方法をめぐって論争している。「西洋」中心の帝国主義下で「下流」とされていた「中国」は、今やビッグデータを操る超大国になった。ウィルス発生源の特定をめぐる攻防、WHOを取り巻く政治的駆け引き、ワクチン開発に関する利害の衝突……。互いに疑いの目を向け合い、激しく対立している。グローバル化が進む世界が一丸となってパンデミックに対抗するには、国家主義を乗り越え、重要な情報や専門知識を積極的に共有しなければならないというのに、どの国も国益を重視する姿勢に傾きがちだ。さらに、感染症をめぐって生じている多くの問題は、「西洋VS非西洋」とか、「中国びいきVSアンチ中国」といった二項対立の文脈からでは解けないものなのに、そこに焦点が集まりがちなのは何故なのか。
ペストと闘う帝国主義下の中国の開港都市、外国人居住地が撤廃されたばかりの神戸、日本の植民地になったばかりの台湾、朝鮮、オランダ統治下のジャワなど、激動の東アジアを記した本書は、歴史研究として重厚さを有しているだけでなく、現在私たちが抱える問いに対しても多くのヒントを投げかけてくれる。
あこ ともこ 現代中国学者、東京大学大学院総合文化研究科教授。
1971年、大阪府生まれ。大阪外国語大学、名古屋大学大学院を経て、香港大学で教育学系Ph.D(博士)取得。在中国日本大使館専門調査員、早稲田大学准教授などを経て、現職。専門は社会学、中国研究。主な著書に『貧者を喰らう国―中国格差社会からの警告』など。

